【行政書士が解説】市街化調整区域って何だろう?
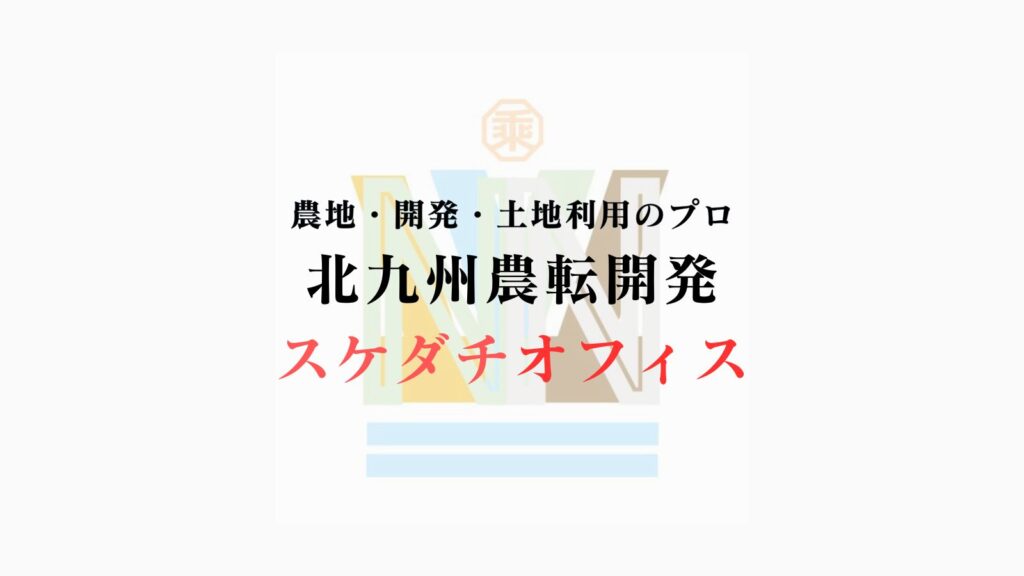
行政書士が市街化調整区域について解説いたします。
農地転用や開発許可、土地の利用関係の許認可に密接に関係する許認可のため十分な理解が必要です。
寄せられる相談の7~8割が市街化調整区域にある農地での手続きです。何をするにも一番最初のハードルとなるのがこの市街化調整区域です。
結構厄介な存在ではありますが、行政書士などの専門家の力を借りることでクリアすることができる可能性も十分にあるため、まずはご相談ください。
市街化調整区域の特徴
市街化調整区域とは、都市計画法に基づき市街化を抑制すべき区域として指定されたエリアです。
都市計画区域内の土地は、市街化を促進する「市街化区域」と市街化を抑制する「市街化調整区域」に区分されます。(都市計画法第7条)
この区分によって都市周辺部の無秩序なスプロール(虫食い的な開発)を防ぎ、計画的なまちづくりを進めることが目的です。
市街化調整区域の特徴については次のようなものがあります。
1.原則として建物を建てることができない(リフォームも原則×)
→市街化調整区域の特徴として大きなものは、原則として建物を建てることができないという点です。
この特徴が大きく関係するのは農地転用(宅地への転用など)と開発許可という許認可です。
市街化調整区域の農地を宅地に転用して自己用住宅を建てたい場合は、農地転用の手続き(農地法)と同時に開発許可の手続き(都市計画法)も取らなければなりません。
これらの許認可は、同時に許可となります。また、これらの許認可はそれぞれ許可が下りる見込みでないと手続きをすることができません。
素人では許可が下りる見込みがあるかどうか判断が難しいため役所での協議も含めて行政書士への相談がおすすめです。
2.土地価格等が比較的安価
→市街化調整区域では、原則として建物を建てることができないため土地の流通性が低く、また近隣は市街化が進んでいないため不便な立地であることが多いです。そのため土地の価格が比較的安価なことが多いです。
3.生活環境は全体的に不便&静か
→市街化調整区域での生活環境は基本的に静かで過ごしやすい環境ではありますが、なんといっても市街化を進めない地域になるので生活必需品を販売する店舗や娯楽に乏しい傾向があります。
市街化調整区域×開発許可制度(都市計画法)
市街化調整区域で土地を宅地造成したり建物を建てたりする場合、都市計画法に基づく開発許可が必要になります(法第29条)
開発許可制度は、無秩序な市街化の防止と良質な宅地の確保を目的としており、市街化調整区域内での開発行為には厳しい基準を課しています 。
市街化調整区域×農地転用(農地法)
市街化調整区域には農地が多く含まれるため、住宅や施設を建てるには農地転用の手続きも避けて通れません。農地転用とは、その名の通り農地を農地以外の用途に変更することです 。例えば田畑を造成して宅地や工場用地にする行為、あるいは地形を変えなくても農地を資材置場にする行為も含まれます。日本では優良農地の保護と農業生産力の維持のため、農地を他用途に転用するには原則として農地法に基づく許可が必要です。
その他関連法令・規制の留意点
市街化調整区域で開発や建築を行う際は、都市計画法と農地法以外にも関連する法令や条例があります。計画段階で包括的にチェックしておきましょう。
建築基準法(建築許可と建築確認): 開発許可を得た場合でも、その後の建築行為には建築基準法に基づく建築確認申請が必要です。建物の構造や設備が耐震・防火など技術基準に適合しているか審査を受け、確認済証の交付を受けなければ着工できません。また、都市計画法の開発許可を伴わない建築行為であっても、市街化調整区域内で建物を新築・用途変更する場合は都市計画法第43条の許可(いわゆる建築許可)を別途取得する必要があります。これは「開発行為を伴わない建築」に対しても無秩序な建築を防ぐために設けられた制度で、開発許可と類似の立地基準に適合することが求められます 。一部の例外(農林漁業用建築物や仮用途の建築など)を除き、調整区域では建築確認前に43条許可を得るのが原則です。福岡県内でも、福岡市など各自治体が43条許可の基準を公表しているので該当する場合は確認してください。なお建築許可の手続きは、既に土地利用が定着している土地に建物を建てるケースが多いため、開発許可より簡易とされていますが、それでも許可なしに建築すると違法建築となりますので注意しましょう。
環境影響評価法・環境保全条例: 開発規模が大きい場合、環境影響評価(環境アセスメント)の対象になることがあります。福岡県では一定規模以上の開発事業(大規模宅地造成や工場建設など)に環境影響評価条例の適用があります。また森林を伐採転用する場合は森林法に基づく林地開発許可、河川や水路に影響を与える場合は河川法や砂防法の許可・協議が必要となることもあります。市街化調整区域は自然環境が豊かな地域が多いため、開発にあたっては周辺環境への配慮が不可欠です。たとえば開発許可の技術基準にも「災害危険区域や急傾斜地崩壊危険区域等の不適地を含まないこと」「1ha以上の開発では樹木や表土の保全措置を講じること」等が定められてお、環境破壊や災害リスクを抑えるよう求められます。実際、農地転用許可基準でも土砂流出防止策や周辺水利への影響について厳しくチェックされます。従って、事前に現地の環境条件(地形・水系・生態系)や法規制を調べ、必要な許認可手続き(例:開発行為が一定規模以上なら環境影響評価の対象か確認)を洗い出しておきましょう。
地方自治体の条例: 上述の福岡県開発許可基準条例のほか、自治体によっては景観条例、地区計画、宅地造成等規制法に基づく条例(擁壁の基準強化など)といったローカルルールが存在します。例えば景観法に基づく景観計画区域では建物デザインや緑化に一定の基準が課されることがあります。また、開発行為で造成した宅地については、完了後に公共施設を市町村へ帰属させる手続きや保安林解除など個別の行政処分も絡む場合があります。福岡県や市町村の関連部署から事前に「関係法令クリアリスト」等の提供を受け、見落としを防ぐことが肝心です。
開発許可・農地転用のポイントとアドバイス
市街化調整区域での土地利用はハードルが高いですが、計画次第では許可取得が可能なケースもあります。最後に、市街化調整区域の土地に関して事業者や個人が押さえておくべき実務上のポイントをまとめます。
① 早めの情報収集と事前相談:そもそも計画地が市街化調整区域や農地の場合は農用地区域に該当するかどうかを都市計画図や農業委員会で早めに確認しましょう。該当する場合は、市町村の担当課や農業委員会に事前相談することが第一歩です。行政は嫌がらず相談に乗ってくれますし、そこで許可の可能性や必要手続きを教えてもらえます。特に調整区域の開発は素人判断が難しいため、「まず相談」が鉄則です。
② 計画のブラッシュアップ:なんにしてもそうですが、行政の定める基準に適切かつ適法に合致する計画でなければ許可はおりません。許認可に裏技はありません。正々堂々と一つ一つのハードルをクリアしていく必要があります。行政への事前相談はもちろん、行政書士などの専門家も間に入れて事業計画をブラッシュアップしましょう。例えば、調整区域で住宅を建てたい場合、自分や親族がその土地に居住する必然性を示す(地域に居住実績がある等)など、第34条第1号に沿うストーリー作りが考えられます。また農地転用では代替地検討や農業継続への配慮(用水路付け替え提案等)を計画書に盛り込むなど、許可担当者がOKを出しやすい計画にブラッシュアップすることが大切です。
③ 必要書類・図面の整備: 開発許可申請書や農地転用許可申請書には、多数の添付資料が求められます (農地転用・開発許可 - 福岡県行政書士会)。役所から案内されるチェックリストに沿って、一つ一つ漏れなく準備しましょう。特に見落としがちなのは公共施設管理者の同意書(道路・上下水道担当課のハンコ)や、隣接農地所有者の承諾書などです。時間がかかる書類もあるため、早めに着手し計画的に収集してください。
④ 専門家の活用: 手続きが煩雑な場合、行政書士や測量士・建築士等の専門家に依頼するのも有効です。農地法・都市計画法に詳しい行政書士は書類作成や役所との協議代行を行っています。実際、他人の依頼で有償で申請書類を作成する行為は行政書士しかできないため(行政書士法)、素人が無理に自作するよりプロに任せた方がスムーズなケースも多いでしょう。費用はかかりますが、許可取得までの時間短縮や不許可リスク低減を買うと考えれば検討に値します。
⑤ 複数許可の調整: 市街化調整区域での土地の利用に関しては、都市計画法の開発許可+農地法の転用許可+建築基準法の確認といったように、事業計画の内容によっては同時多発的に複数の許認可が関係します。基本的には、これらはそれぞれ別個の手続きですが、関連し合う部分もあります。例えば農地転用許可が下りないと開発許可もおりません。許認可の専門家は行政書士です。お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
お問合せの前によくあるご質問もご確認ください。
お電話の場合
年中無休:9時~20時
お問い合わせフォーム
LINEでのお問い合わせも可能

対応可能エリア
福岡県全域対応いたします
※弊所が北九州市にある関係でスケジュールによっては対応に1~2営業日いただく地域がございます。
【最短即日対応可能エリア】
北九州市・芦屋町・水巻町・中間市・遠賀町・岡垣町・苅田町・みやこ町・行橋市
【スケジュールによっては最短即日対応可能エリア】
築上町・豊前市・吉富町・上毛町・鞍手町・直方市・福智町・香春町・糸田町・田川市・大任町・赤村・添田町・川崎町・嘉麻市・桂川町・飯塚市・小竹町・宮若市・宗像市・福津市・古賀市・新宮町
【2営業日以内に対応可能エリア】
久山町・粕屋町・須恵町・志免町・宇美町・太宰府市・筑紫野市・大野城市・春日市・那珂川市・福岡市・糸島市・筑前町・朝倉市・東峰村・小郡市・大刀洗町・うきは市・久留米市・広川町・八女市・筑後市・大木町・大川市・柳川市・みやま市・大牟田市
【大分県全域】
大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市
豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、姫島村、日出町、九重町、玖珠町
【山口県全域】
下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市
周南市、山陽小野田市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町
投稿者プロフィール
最新の投稿
 太陽光パネル名義変更2025年12月17日【行政書士監修】福岡県行橋市の住宅用太陽光パネルの名義変更手続きはお任せください
太陽光パネル名義変更2025年12月17日【行政書士監修】福岡県行橋市の住宅用太陽光パネルの名義変更手続きはお任せください 北九州2025年12月17日【行政書士監修】福岡県北九州市で住宅用太陽光パネルの名義変更はお任せください
北九州2025年12月17日【行政書士監修】福岡県北九州市で住宅用太陽光パネルの名義変更はお任せください 事務所からのお知らせ2025年10月6日宅地造成技術講習を修了しました
事務所からのお知らせ2025年10月6日宅地造成技術講習を修了しました 事務所からのお知らせ2025年9月20日事務所名等の変更のお知らせ
事務所からのお知らせ2025年9月20日事務所名等の変更のお知らせ

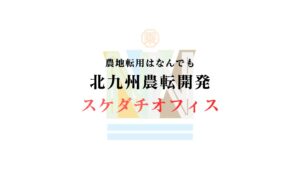
“【行政書士が解説】市街化調整区域って何だろう?” に対して3件のコメントがあります。